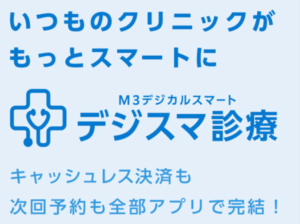こんにちは、大阪の頭痛外来のある「いわた脳神経外科クリニック」です。
当院に来られる片頭痛の患者さんの中には耳鳴りの症状を訴える方がいます。実は、片頭痛の前兆として耳鳴りが関係していることをご存知でしょうか。
今回は、片頭痛と耳鳴りの関係や、頭痛に困ったときの対処法・予防法について解説していきます。 耳鳴りと頭痛の症状で悩まれている方の参考になれば幸いです。

片頭痛と耳鳴りにはどんな関係がある?
片頭痛と耳鳴りには、密接な関係があることをご存知でしょうか。片頭痛と耳鳴りの関係と耳鳴りをともなう頭痛で受診する際に気をつけたいポイントをお伝えします。
片頭痛と耳鳴りの関係
耳鳴りの症状をもつ患者さん193例を対象とした研究では、44.6%が片頭痛だったという結果が出ています。[1]また、片頭痛と耳鳴りの連動がある症例の頻度を調べた研究によると、耳鳴りにおける症例の約30%が頭痛を併発しており、そのうちの大半が片頭痛だったという報告があります。
耳鳴りをともなう片頭痛の原因は、頭の血管の収縮・拡張との関連が示唆されています。近年では頭の中の血管に分布している三叉神経から放出されるカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)と呼ばれる物質が関係することもわかってきました。[2]
耳鳴りをともなう頭痛:受診時のポイント
片頭痛は耳鳴りや難聴を併発しやすいのが特徴です。また、片頭痛と耳鳴りの症状が連動するケースは、耳鳴りの重症度が高くなる傾向にあります。そのため、耳鳴りを訴える患者さんに対しては、頭痛のスクリーニングが必要であると考えられています。[3]
受診の際には耳鳴りと合わせて、どのような頭痛が起こるか、以下の点を詳しく医師に伝えることが大切です。

「耳鳴り」の症状について、こちらでも詳しく解説しています。
片頭痛の前兆として耳鳴りが起こることも
片頭痛の前兆として、耳鳴りが起こることが明らかになっています。
片頭痛でみられる前兆
片頭痛の前兆には、視覚症状(閃輝暗点)・感覚症状(チクチクする、感覚が鈍くなる)・言語症状(ろれつが回りにくい)などの「典型的前兆」があります。
また、片麻痺性片頭痛の前兆では、典型的前兆の症状に加え、運動麻痺(脱力)が起こります。脳底型片頭痛の前兆としては、めまい・耳鳴り・難聴などが起こるのが特徴です。[2]
「閃輝暗点」とピルの関係は次の記事で詳しく説明しています。
片頭痛の前兆に耳鳴りが起こる理由
これまでの研究により、片頭痛の前兆は、皮質拡延性抑制(大脳皮質における神経細胞やそれ以外の細胞が突如活性化し、同心円状に活性化が広がった後、神経細胞の働きが低下する現象)が大脳に生じて起こると考えられています。[4]しかし、原因ははっきりと解明されていません。
耳鳴りをともなう片頭痛の対処法
片頭痛は、頭の片側が脈と同じタイミングで痛むのが特徴です。一度痛みが現れると4〜72時間持続します。運動や音・光に過敏に反応するため、[2]頭の痛みに困った際は以下の内容を実践してみてください。
音や光を遮断する
片頭痛を誘発する要素である音や光から刺激を受けないよう、静かな暗い部屋で過ごしましょう。どうしても落ち着いて過ごせる部屋がない場合は、アイマスクや耳栓などをして、外からの刺激を遮断することも大切です。症状が和らぐまでは、スマホやPCなどの光を発するものの操作も控えた方がよいでしょう。

静かに過ごす
片頭痛は運動で症状が悪化しやすい傾向にあります。歩行や、階段の昇り降りなどの日常的な動作でも頭痛がひどくなりやすいので、外出はもちろん、家事も控えて安静に過ごしましょう。横になるなど、頭痛が和らぐ姿勢をとり、体をゆっくりと休めましょう。

カフェインを含む飲み物を飲む
カフェインには片頭痛に対する効果が示されており、軽症の片頭痛発作時に痛みを鎮める薬として用いられます。 [5] カフェインを含むコーヒーや紅茶などを飲むと、一時的に片頭痛が和らぐでしょう。
ただし、過度に摂取すると睡眠不足につながり、余計に片頭痛を悪化させる要因になります。目安として、コップ1杯程度に留めておくことをおすすめします。

耳鳴りをともなう片頭痛の予防法
耳鳴りをともなう片頭痛を予防する方法を解説します。日頃から片頭痛に悩まされている方は、以下の方法で頭の痛みを予防しましょう。
適度な睡眠時間を確保する
片頭痛を訴える患者さんの約30%は睡眠不足といわれています。睡眠の摂りすぎも頭痛の要因になり得ます。[2]
厚生労働省によると、7時間より短時間または長時間の睡眠は、生活習慣病やうつ病の発症、死亡に至るリスクが増加するとあります。[6]健康を維持するために、毎日7時間を目安に睡眠時間を確保しましょう。

食生活に配慮する
片頭痛を誘発するおそれがある食品として、赤ワイン・チーズ・チョコレート・柑橘類・ナッツ類が挙げられます。片頭痛の慢性化には、肥満も関連しています。片頭痛の原因となる食品をなるべく控え、食べ過ぎに注意し、適正体重を維持することが大切です。[2]

ストレスケアを心がける
片頭痛を訴える患者さんの約60%は、ストレスがあるときに発症するといいます。[2] そのため、日頃からストレス対策を心がけることが大切です。
趣味の時間に没頭したり、定期的な運動をしたりしてリフレッシュする時間を確保しましょう。良質な睡眠も必要です。就寝の1~2時間前に入浴すると入眠しやすくなります。[6]
片頭痛を治すために適切な治療を
耳鳴りは片頭痛の前兆となる症状の1つです。耳鳴りが起きたときは、片頭痛を併発するおそれがあります。片頭痛が気になる方は、日頃から適度な睡眠時間を確保し、ストレスケアや食生活に配慮して日々を過ごしましょう。
片頭痛の薬物治療としては、発作時の痛みを抑える治療が主流でした。近年、「ヒト化抗 CGRP モノクローナル抗体製剤(「CGRP」頭痛薬剤)」を用いた治療という選択肢が増えています。
この治療では、片頭痛の発症や症状の悪化に影響を与える神経伝達物質であるカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)の活性を抑え、片頭痛発作の低減が期待できます。
片頭痛の治療について詳しくはで解説しています。
「CGRP」頭痛薬剤を用いた治療は保険診療です。
当院の院長は大阪市にある複数の基幹病院で脳神経外科の診療を担当しています。当院の頭痛外来では、多くのの頭痛に悩む患者さんの診療に携わり、お一人おひとりの頭痛のお悩みやライフスタイル合わせた治療に努めています。
日々の頭痛に悩み、対処法や治療法がわからずお困りの方は、大阪市城東区ののある「いわた脳神経外科クリニック」にご相談ください。
参考リンク
[1] 五島史行,岩倉昌岐 頭痛患者における耳鳴について 日本頭痛学会誌vol.50 p.148―151 2023https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjho/50/1/50_148/_pdf/-char/ja
[2] 慢性頭痛の診療ガイドライン作成委員会|慢性頭痛の診療ガイドライン2013https://www.jhsnet.net/GUIDELINE/gl2013/gl2013_main.pdf
[3] 蒲谷嘉代子ら 耳鳴患者における頭痛の併存とその影響 Audiology Japan vol.65 p.201~208, 2022https://www.jstage.jst.go.jp/article/audiology/64/5/64_377/_pdf
[4] 鈴木則宏ら 片頭痛前兆大脳皮質拡延性抑制が神経障害性疼痛を惹起する脳可塑性と疼痛制御系の解明 科学研究費補助金研究成果報告書2014年度(2019) [5] 北川泰久ら 頭痛治療のトピックス 日内会誌 102 p.1907~1915 2013https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/102/8/102_1907/_pdf
[6] 厚生労働省|健康づくりのための睡眠ガイド 2023https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
あなたも『頭痛から卒業』を目指して一緒に治療しませんか?
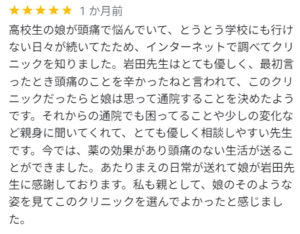
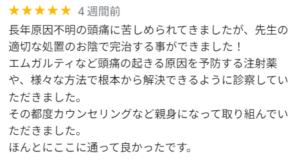
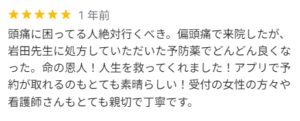
ご予約・お問い合わせはこちらから
一度診察を希望の方は、下記デジスマ診療をクリックしてご予約くださいませ。
また当院公式LINEにてご質問等をお受けしておりますので、
お気軽にお問い合わせくださいませ。