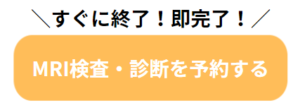突然、顔がしびれたり動かしにくくなったりすると、とても不安になりますよね。顔面の麻痺やしびれは日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、時に重大な病気のサインである場合があります。しかし、顔面麻痺が起きた時、どの診療科を受診すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、顔面に麻痺やしびれが生じた場合の適切な受診先や、考えられる主な原因疾患について詳しく解説します。症状の特徴や緊急度の判断なども含め、いざという時に慌てずに正しい対応ができるよう、必要な知識をわかりやすくまとめました。
顔面麻痺の症状が出たときに受診すべき診療科
顔面に麻痺やしびれの症状が現れたとき、どの診療科を受診すべきか悩むことがあります。実際には、症状の特徴や原因によって適切な診療科が異なります。
脳神経内科・神経内科が適切なケース
顔面麻痺が脳の病気に関連している場合は、脳神経内科(または神経内科)の受診が適切です。特に顔面麻痺と同時に、手足のしびれや麻痺、言語障害、めまい、強い頭痛などの症状がある場合は脳の病気が疑われます。
脳神経内科では、脳卒中(脳梗塞・脳出血)や多発性硬化症などの神経疾患の診断と治療を専門としています。医師は神経学的検査や画像診断(MRIやCTなど)を行い、症状の原因を特定します。
脳卒中などの緊急性の高い疾患が疑われる場合は、迷わず救急車を呼ぶことが生命を守る重要なポイントです。特に片側の顔面麻痺に加えて、手足の麻痺や話しづらさがある場合は一刻も早く医療機関を受診してください。
耳鼻咽喉科が適切なケース
顔面神経麻痺のみが症状の場合、特にベル麻痺(原因不明の顔面神経麻痺)や耳の周囲の違和感・痛みを伴う場合は、耳鼻咽喉科を受診するのが適切です。
耳鼻咽喉科では、顔面神経の機能を評価するための筋電図検査や、耳の状態を確認する検査が行われます。ベル麻痺やハント症候群(帯状疱疹ウイルスによる顔面神経麻痺)などの診断と治療が可能です。
顔面麻痺が突然発症し、それ以外の神経症状がない場合は、早期の耳鼻咽喉科受診が推奨されます。治療の開始が早いほど、回復の見込みが高くなる傾向があります。
脳神経外科が適切なケース
顔面麻痺の原因が脳腫瘍や頭部外傷、頭蓋内の血管異常などの場合は、脳神経外科の受診が適切です。これらの疾患は画像検査で診断され、外科的治療が必要となる場合があります。
脳神経外科では、MRIやCTなどの画像検査を行い、顔面神経に影響を与えている病変を特定します。必要に応じて手術的治療も検討されます。
頭部打撲後の顔面麻痺や長期間にわたって進行する顔面麻痺の場合は、脳神経外科を受診することが望ましいでしょう。特に徐々に進行する症状がある場合は、腫瘍などの可能性も考慮して精密検査を受ける必要があります。
症状が複雑であったり、原因が不明瞭な場合は、まず総合内科や総合診療科を受診するのも一つの選択肢です。そこで初期評価を受け、適切な専門科へ紹介してもらうことができます。
大きな病院では、初診時に総合診療科や救急外来を受診し、その後専門科へ振り分けられるシステムを採用していることが多いです。また、病院によっては顔面神経麻痺外来など、特化した専門外来を設けているところもあります。
不安な場合は、まず電話で病院に相談し、症状に適した診療科を確認するとよいでしょう。
顔面麻痺の原因となる疾患
顔面に起こる麻痺やしびれには、さまざまな原因があります。原因によって症状の特徴や緊急性も異なるため、正確な理解が大切です。
ベル麻痺(特発性顔面神経麻痺)
ベル麻痺は、明確な原因が特定できない顔面神経麻痺で、顔面麻痺の中で最も一般的な原因とされています。一般的には一側の顔面に急に発症し、目が閉じにくい、口角が下がる、食事の際に水が漏れるなどの症状が特徴です。
ベル麻痺は寒冷や疲労、ストレスなどをきっかけに発症することがあり、ウイルス感染が関与していると考えられています。多くの場合、数週間から数ヶ月で自然回復しますが、早期のステロイド治療が回復を促進するとされています。
ベル麻痺の場合、発症から48時間以内にステロイド治療を開始することで回復率が高まるため、症状に気づいたらできるだけ早く医療機関を受診することが重要です。
ハント症候群(耳帯状疱疹)
ハント症候群は、水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化によって起こる疾患です。顔面神経麻痺に加えて、耳の周囲や口の中に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現し、耳の痛みやめまい、難聴などを伴うことが特徴です。
治療には抗ウイルス薬とステロイド薬の併用が行われます。ベル麻痺と比較して回復に時間がかかることが多く、完全回復が難しいケースもあります。
耳の痛みが先行して現れ、その後顔面麻痺が出現するパターンが典型的です。早期の治療開始が予後改善につながるため、耳の痛みと顔面の違和感を同時に感じた場合は、できるだけ早く耳鼻咽喉科を受診しましょう。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)
脳卒中による顔面麻痺は、脳の運動神経を支配する領域(主に中大脳動脈領域)が障害されることで発生します。この場合、顔面麻痺だけでなく、手足の麻痺や言語障害など他の神経症状を伴うことが特徴です。
脳卒中の場合、中心性(上位運動ニューロン)顔面麻痺と呼ばれる特徴があり、額のしわ寄せは保たれることが多いです。これはベル麻痺などの末梢性顔面麻痺と区別する重要なポイントになります。
脳卒中は一刻も早い治療開始が必要な緊急疾患です。顔面麻痺と共に、突然の手足のしびれや麻痺、ろれつが回らない、激しい頭痛などの症状がある場合は、すぐに救急車を呼びましょう。
脳腫瘍
聴神経腫瘍(前庭神経鞘腫)や髄膜腫などの脳腫瘍が顔面神経を圧迫することで、顔面麻痺が生じることがあります。腫瘍による顔面麻痺の特徴は、ゆっくりと進行することが多く、難聴やめまいなどの症状を伴うことがあります。
脳腫瘍による顔面麻痺の場合、MRIなどの画像検査で診断され、腫瘍の種類や大きさ、位置に応じて手術や放射線治療などが行われます。
徐々に進行する顔面麻痺や、麻痺が長期間(3ヶ月以上)改善しない場合は、脳腫瘍などの構造的な原因がないか精査する必要があります。
多発性硬化症
多発性硬化症は、中枢神経系の脱髄疾患で、脳や脊髄のさまざまな部位に病変が生じる自己免疫疾患です。顔面麻痺は多発性硬化症の症状の一つとして現れることがあり、他の神経症状(視力障害、感覚障害、運動障害など)を伴うことが特徴です。
多発性硬化症の診断には、MRI検査や脳脊髄液検査などが行われます。治療には免疫調整薬や免疫抑制薬などが用いられ、再発予防が重要となります。
顔面麻痺が他の神経症状と共に繰り返し発生する場合や、MRI検査で特徴的な所見がある場合は、多発性硬化症が疑われます。
顔面麻痺の緊急度を判断するポイント
顔面麻痺が生じた場合、その原因によっては緊急の医療介入が必要な場合もあります。自分や家族の症状が緊急性が高いかどうかを判断するポイントを知っておくことが大切です。
すぐに救急車を呼ぶべき症状
顔面麻痺に加えて、以下の症状がある場合は脳卒中などの緊急性の高い疾患の可能性があるため、すぐに救急車を呼ぶべきです。
- 突然の片側の手足の麻痺やしびれ
- 言葉が出にくい、ろれつが回らない
- 突然の激しい頭痛
- 急なめまいや歩行困難
- 視野の異常(視界の一部が見えないなど)
- 意識障害(もうろうとする、反応が鈍いなど)
脳卒中は「時間との戦い」であり、発症から治療開始までの時間が短いほど後遺症が少なくなる可能性が高まります。上記の症状がある場合は自力で病院に行こうとせず、すぐに119番通報しましょう。
当日中に受診すべき症状
緊急ではないものの、当日中に医療機関を受診すべき症状には以下のようなものがあります。
- 突然発症した顔面麻痺(他の神経症状を伴わない場合でも)
- 耳の周囲の痛みや水疱を伴う顔面麻痺
- 目が完全に閉じられない状態
- 顔面の感覚異常が強い場合
ベル麻痺やハント症候群の場合、早期治療(特に発症48時間以内のステロイド治療)が予後に影響するため、症状に気づいたらできるだけ早く医療機関を受診することが重要です。
数日以内に受診すべき症状
以下のような症状がある場合は、数日以内に受診を検討しましょう。
- 軽度の顔面の違和感や動きにくさ
- 顔面麻痺が数日かけて徐々に進行している
- 過去に顔面麻痺があり、症状が再発した
症状が軽度であっても、適切な診断と治療を受けることで回復が早まる可能性があります。特に、顔面麻痺が徐々に進行している場合は、腫瘍などの可能性も考慮して検査を受ける必要があります。
自己判断の注意点
顔面麻痺の原因は多岐にわたるため、素人判断で重症度を決めつけることは危険です。特に以下のような場合は注意が必要です。
- 「単なる疲れだろう」と自己判断して様子を見る
- 「前にも同じような症状があったが自然に治った」と過去の経験だけで判断する
- インターネットの情報だけで診断や治療を決める
顔面麻痺は適切な診断と早期治療が重要なため、症状があれば自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。特に初めて経験する症状の場合は、専門家の診断を受けましょう。
顔面麻痺の検査と診断方法
顔面麻痺の原因を特定するためには、様々な検査が行われます。どのような検査が行われるのか、事前に知っておくと安心です。
初診時の診察と問診
顔面麻痺の診断では、まず詳細な問診と神経学的診察が行われます。医師は以下のような点を確認します。
- 症状がいつから始まったか
- 麻痺の進行速度(突然か、徐々にか)
- 痛みや他の症状の有無
- 過去の既往歴(高血圧、糖尿病、自己免疫疾患など)
- 最近の感染症やストレス、外傷の有無
診察では、顔の表情筋の動きを確認します。額にしわを寄せる、目を強く閉じる、口を横に引くなどの動作を指示され、左右差がないかチェックされます。
問診時には症状の発症状況をできるだけ詳しく伝えることが正確な診断につながります。症状の変化や気になる点はメモしておくと役立つでしょう。
画像検査(MRI・CT)
顔面麻痺の原因を特定するために、MRIやCTなどの画像検査が行われることがあります。特に以下のような場合は画像検査が重要です。
- 脳卒中が疑われる場合
- 腫瘍が疑われる場合
- 外傷後の顔面麻痺
- 複数の神経症状を伴う場合
- 通常の治療で改善しない場合
MRIは軟部組織の詳細な画像が得られるため、神経や脳の細かい病変を確認するのに適しています。一方、CTはより短時間で撮影でき、出血や骨の異常を確認するのに役立ちます。
画像検査は痛みを伴わない検査ですが、MRIは閉所恐怖症の方には負担になることがあります。また、体内に金属がある方はMRI検査ができない場合があるため、事前に医師に伝えておく必要があります。
神経伝導検査・筋電図
神経伝導検査や筋電図は、顔面神経の機能を客観的に評価する検査です。これらの検査では以下のことが分かります。
- 神経損傷の程度
- 神経変性の有無
- 回復の可能性の予測
- 経時的な機能回復の評価
特にベル麻痺やハント症候群などの末梢性顔面神経麻痺の評価に有用で、発症から2週間前後で行われることが多いです。検査結果は予後予測や治療方針の決定に役立ちます。
検査中は微弱な電気刺激を与えたり、細い針電極を筋肉に挿入したりするため、軽度の不快感を伴うことがありますが、短時間で終わる検査です。
血液検査・その他の検査
顔面麻痺の原因によっては、以下のような追加検査が行われることがあります。
- 血液検査:炎症マーカー、糖尿病、自己免疫疾患などの確認
- 髄液検査:多発性硬化症やギラン・バレー症候群が疑われる場合
- 聴力検査:ハント症候群や聴神経腫瘍が疑われる場合
- 平衡機能検査:めまいを伴う場合
特に若年者で原因不明の顔面麻痺が繰り返す場合や、他の神経症状を伴う場合は、より広範囲な検査が必要になることがあります。
検査の目的や必要性について不明点があれば、医師に遠慮なく質問することが大切です。検査結果をもとに最適な治療計画が立てられます。
まとめ/h2>
顔面に麻痺やしびれが生じた場合、その症状に応じて適切な診療科を選ぶことが重要です。顔面麻痺のみの場合は耳鼻咽喉科、他の神経症状を伴う場合は脳神経内科、構造的な問題が疑われる場合は脳神経外科が適切な選択となります。
顔面麻痺の原因は多岐にわたりますが、早期の適切な診断と治療が良好な回復につながります。特にベル麻痺やハント症候群では早期のステロイド治療が重要であり、脳卒中のような緊急性の高い疾患では迅速な処置が必要です。
麻痺やしびれの症状に気づいたら「大丈夫だろう」と自己判断せず、適切な医療機関を受診しましょう。特に他の神経症状を伴う場合や突然の激しい頭痛がある場合は緊急性が高いため、救急車を呼ぶことを躊躇しないでください。適切な医療と継続的なケア、リハビリテーションによって、多くの場合良好な回復が期待できます。
お問い合わせはこちらから
また当院公式LINEにてご質問等をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。