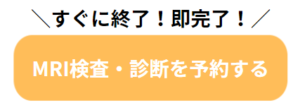| 用量 | 1本のみ | 4本セット | 12本セット |
|---|---|---|---|
| 2.5mg | 4,980円 | 19,920円 (4,980円/本) |
47,760円 (3,980円/本) |
| 5.0mg | 9,900円 | 35,000円 (8,750円/本) |
92,400円 (7,700円/本) |
| 7.5mg | 14,300円 | 49,800円 (12,450円/本) |
118,800円 (9,900円/本) |
| 10.0mg | 18,700円 | 65,000円 (16,250円/本) |
180,000円 (15,000円/本) |
※ 表示価格は税込。12.5mg・15mgの取扱いは医師へご相談ください。
ご予約・お問い合わせ
いわた脳神経外科クリニックでは、医師管理のもと安全にマンジャロ治療を行っています。
まずはお気軽にご相談ください。
「つらい関節の痛みに加えて、頭痛にも悩まされている…」。それは偶然ではなく、あなたの体が発している重要なサインかもしれません。
この記事では、脳神経外科医の視点から、関節の痛みと同時に起こる頭痛について、信頼できる情報だけを厳選して解説します。もう一人で悩まず、正しい知識でつらい症状を和らげる一歩を踏み出しましょう。
1. 【研究結果】頭痛と関節痛の深い関係性とは?
関節の痛みと頭痛が同時に起こることには、科学的な理由があります。ここでは、大規模な調査研究で明らかになった事実と、その背景にある体のメカニズムについて詳しく解説します。
1-1 統計が示す「関節炎と片頭痛」の驚くべき関連性
2021年に発表された米国の成人2,649人を対象とした大規模な調査研究(Jacob et al.)では、「関節炎」と「片頭痛」の間に非常に強い関連があることが統計的に証明されました。具体的には、関節炎を持つ人は、そうでない人と比べて片頭痛を発症する確率が約2倍高いことが明らかになったのです。
さらに興味深いのは、この関係が「双方向」である可能性が示唆された点です。つまり、「片頭痛を持つ人が後に関節炎を発症する」という逆のパターンも考えられるということです。これは、2つの症状が単なる偶然の併発ではなく、体の内部で共通のメカニズムを介してつながっていることの強力な証拠と言えます。
| 研究対象 | 主な発見 | 意味すること |
|---|---|---|
| 米国成人 2,649人 | 関節炎を持つ人は片頭痛のリスクが約2倍 | 関節痛と頭痛は偶然ではなく、医学的に関連している |
1-2 なぜ関連が?考えられる共通のメカニズムは「全身の炎症」
では、なぜ関節炎と片頭痛は関連するのでしょうか。最も有力な説は、両者の根底に「全身性の炎症」が存在するというものです。特に関節リウマチのような自己免疫疾患では、免疫システムの異常により、サイトカインと呼ばれる炎症を引き起こす物質が体内で過剰に作られます。
このサイトカインは、いわば「炎症の火種」です。関節で発生した火種が血流に乗って全身を巡り、脳に到達すると、脳の血管や硬膜(脳を覆う膜)、三叉神経といった痛みに敏感な組織を刺激します。その結果、片頭痛特有のズキンズキンとした拍動性の痛みが引き起こされると考えられています。つまり、関節で起きている火事(炎症)の煙が、脳にまで達して警報(頭痛)を鳴らしているような状態なのです。
1-3 痛み止めが新たな頭痛を呼ぶ「薬剤の使用過多による頭痛」
関節痛を和らげるために、市販の非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)などを日常的に服用している方は、特に注意が必要です。月に10日〜15日以上など、鎮痛薬を使いすぎると、脳が痛みをコントロールするシステムに異常が生じ、かえって痛みに過敏になってしまうことがあります。その結果、薬を飲んでも効きにくくなり、ほぼ毎日続くような鈍い頭痛が起こるようになります。
注意:薬剤の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)
これを「薬剤の使用過多による頭痛(Medication-Overuse Headache)」と呼びます。良かれと思って飲んでいる薬が、新たな苦しみの原因になるという悪循環です。この状態から抜け出すには、原因となっている薬剤を一度中止する必要がありますが、自己判断は危険です。必ず医師や専門家にご相談ください。
2. 【2024年最新情報】関節痛を軽減するためのアプローチ
関節痛、特に生活の質を大きく下げる変形性膝関節症の治療は日々進歩しています。ここでは、2024年に発表された画期的な研究報告を中心に、効果的なアプローチを詳しくご紹介します。
2-1 肥満と膝の痛みに新選択肢「セマグルチド」の驚くべき効果
2024年10月、肥満を伴う変形性膝関節症の治療に光を当てる画期的な研究(Bliddal et al.)が発表されました。この研究では、肥満(BMI30以上)の患者に、週1回「セマグルチド」(GLP-1受容体作動薬)を投与し、その効果を検証しました。
結果は非常に目覚ましいものでした。68週間の治療後、セマグルチドを投与されたグループは、偽薬(プラセボ)のグループと比較して、体重と膝の痛みの両方で劇的な改善を示したのです。
| 評価項目 | セマグルチド群 | プラセボ群 |
|---|---|---|
| 平均体重減少率 | -13.7% | -5.1% |
| 膝の痛みスコア(WOMAC)の変化 ※スコアが低いほど改善 | -41.7点 | -27.5点 |
| 身体機能スコア(WOMAC)の変化 ※スコアが低いほど改善 | -37.3点 | -23.7点 |
※WOMACスコアは、変形性関節症の痛みや身体機能を評価する国際的な指標(0〜100点)。
膝の痛みスコア(WOMAC)の改善度比較
この結果は、単に体重が減って膝への物理的な負担が軽くなっただけでなく、セマグルチド自体が持つ「抗炎症作用」も痛みの改善に寄与している可能性を示唆しています。肥満を合併する膝の痛みに対して、非常に有望な新しい治療選択肢と言えるでしょう。
2-2 すべての基本となるセルフケア|食事・運動・ストレス管理
治療も重要ですが、その効果を最大限に引き出すためには、日々のセルフケアが不可欠です。炎症を抑え、痛みをコントロールするための3つの柱をご紹介します。
- 食事:抗炎症作用のあるオメガ3脂肪酸が豊富な青魚(サバ、イワシなど)、抗酸化物質を多く含む緑黄色野菜やベリー類、ナッツ類を積極的に摂りましょう。逆に、炎症を促進するトランス脂肪酸(マーガリンなど)や糖分の多い加工食品、清涼飲料水は控えることが賢明です。
- 運動:痛いからと動かないでいると、筋力が低下し、さらに関節が不安定になります。専門家の指導のもと、膝に負担の少ない水中ウォーキングやサイクリング、関節を支える大腿四頭筋を鍛えるトレーニングを継続することが、痛みの軽減に直結します。
- ストレス管理:慢性的な痛みはそれ自体が大きなストレスとなり、交感神経を刺激して血管を収縮させ、痛みをさらに悪化させます。1日5分でも良いので、深呼吸や瞑想、好きな音楽を聴くなど、意識的に心身をリラックスさせる時間を作ることが、痛みの悪循環を断ち切る助けとなります。
Q. 関節リウマチと片頭痛には関連がありますか?
A. はい、非常に強い関連性が医学研究で報告されています。関節リウマチの根本原因である「全身の炎症」が、脳の血管や神経を刺激し、片頭痛の引き金になると考えられています。そのため、リウマチ自体の治療を適切に行い炎症を抑えることが、頭痛の改善にもつながる可能性があります。
Q. セマグルチドが含まれる薬品には何がありますか?
A. セマグルチドは、日本では「ウゴービ®」(肥満症治療薬)や「オゼンピック®」(2型糖尿病治療薬)、「リベルサス®」(2型糖尿病治療薬)といった商品名で承認・販売されています。いずれも医師の処方が必要な医療用医薬品であり、自己判断での使用はできません。変形性膝関節症への適用は最新の研究に基づくものであり、治療を希望される場合は必ず専門医にご相談ください。
Q. 痛みがあるとき、運動はしても良いのでしょうか?
A. はい、ただし医師や理学療法士の指導のもと、適切な運動を行うことが重要です。痛みを悪化させないためには、水中ウォーキングや固定式自転車など、関節に体重の負荷がかかりにくい運動が推奨されます。筋肉は関節を守るサポーターの役割を果たすため、無理のない範囲で筋力を維持・向上させることが、長期的に痛みを和らげる鍵となります。
Q. ウゴービ®が処方される条件は?
A. 肥満症治療薬のウゴービ®は、食事療法・運動療法を行っても効果が不十分な場合に、以下のいずれかの条件を満たす方が保険適用の対象となります。
- BMIが35kg/m²以上の高度肥満の方
- BMIが27kg/m²以上で、かつ高血圧、脂質異常症、2型糖尿病のいずれか2つ以上の健康障害(合併症)を有する方
※処方には医師による詳細な診断が必要です。ご自身の状態が当てはまるかについては、専門の医療機関でご相談ください。
4. まとめ:関節痛と頭痛の悪循環を断ち切るために
関節痛と頭痛が同時に起こるのは、決して気のせいではありません。その背景には「全身の炎症」や「鎮痛薬の使いすぎ」といった、明確な医学的根拠が存在します。
幸いなことに、セマグルチドのような治療法の登場により、特に肥満を伴う膝の痛みに対しては、未来への大きな希望が見えてきました。
最も重要なことは、ご自身の症状を正しく理解し、一人で抱え込まずに専門医に相談することです。整形外科、リウマチ科、そして頭痛が続く場合は脳神経外科や頭痛外来の受診もご検討ください。適切な診断と治療計画のもと、つらい痛みの悪循環を断ち切り、健やかな毎日を取り戻しましょう。
お問い合わせはこちらから
当院では、肥満症治療薬として、ウゴービやマンジャロを取り扱いしております。また当院公式LINEにてご質問等をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
参考文献
Bliddal, H. et al. (2024) ‘Once-Weekly Semaglutide in Persons with Obesity and Knee Osteoarthritis’, New England Journal of Medicine, 391(17), pp. 1573–1583. doi: 10.1056/NEJMoa2403664.
Jacob, L. et al. (2021) ‘Association between arthritis and migraine: a US nationally representative study including 2649 adults’, Journal of Clinical Medicine, 10(2), p. 342. doi: 10.3390/jcm10020342.